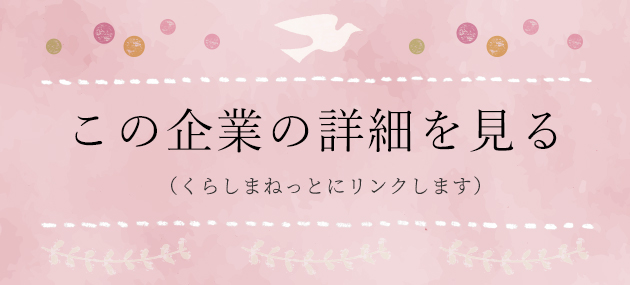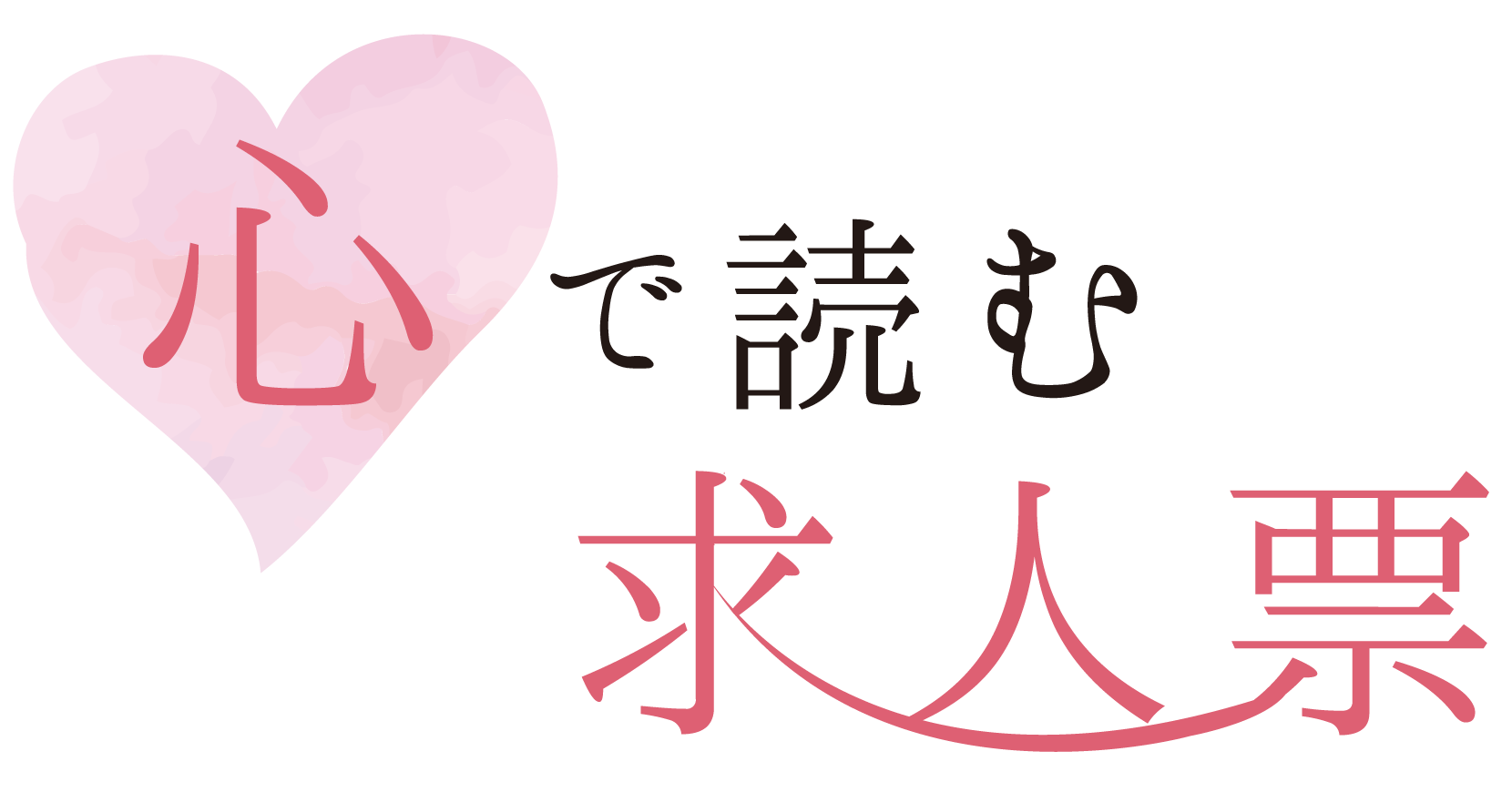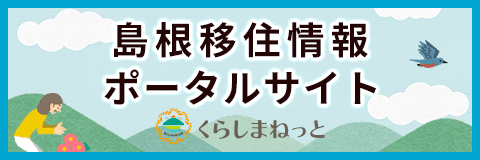株式会社アイティーエスピーの求人情報
必要なのは、未知の世界へ飛び込む勇気と熱意。
ITエンジニアの挑戦の機会がここにある。
アプリケーション開発(島根県 出雲市)


古くから神々が集う地として知られる島根県出雲市は、神話とテクノロジーが共存するユニークな都市です。
株式会社アイティーエスピー(以下、アイティーエスピー)は、出雲市のIT産業を支える企業の一つです。JR出雲市駅から徒歩1分という好立地にオフィスを構え、東京都台東区の本社(御徒町駅徒歩3分)、大阪オフィス(本町駅徒歩10分)とあわせて、主に3つの拠点で活動しています。
今回訪れた島根出雲オフィスでは、首都圏からのニアショア開発を軸に、Webアプリ開発、Webサービス開発、システムコンサルティングなど、高度な知識や技術力を要するプロジェクトを数多く手掛けています。社員一人ひとりの可能性を引き出し、チームを成功へと導くアイティーエスピーの舵取り役を担うのが、代表取締役の松島秀彰さんです。
松島代表はITという枠にとらわれず、地域を巻き込んだイベント(講演会、気球フェスなど)の開催や飲食店(バー)の経営など、新しい取り組みに次々と挑戦。そうして得た知見やネットワークが、柔軟な発想や社員のモチベーション向上にも繋がっているようです。こうした取り組みは地域の活性化にも一役買っており、地元住民からも信頼を寄せられています。
そんな「まだやったことがないことへの挑戦」を大切にしている松島代表に、アイティーエスピーの魅力や人材育成に対する想いを伺いました。

Q.事業内容についてお聞かせください。

主に、Ruby、Java、C#等を使用して、Webアプリケーションの開発を行っており、医療機関向けオンライン診療アプリの開発、金融商品に関するWebサービスの開発など、幅広く手掛けております。
最近では、地元企業のシステムコンサルティングのお仕事も増えてきており、実際の開発も社内で行っています。
システム開発、アプリケーション開発におけるニーズがますます多様化していくなか、
"お客様と共に成長"をスローガンに、顧客の課題解決に貢献しているアイティーエスピー。ハイレベルな案件も多いことから、上流工程を担うSEや高い技術力を持ったプログラマーの採用を強化している一方で、IT業界に初めてチャレンジする未経験者の採用も積極的に進めています。その背景にはどのような考えがあるのでしょうか。


まず、弊社は「実務経験はないけど、IT業界に挑戦したい」という想いを持っている方に、その挑戦の機会を提供する企業でありたいと思っています。
実は私自身も24歳の時に、実務未経験ながらエンジニア志望としてこの業界に入りました。
2014年からなのでこの業界は約10年になりますが、たくさんのエンジニアに会ってきました。
私は、実際はエンジニアではなく、営業という役割で活動してきたのですが、営業という立場上多くのエンジニアに会います。また、経営者になってからはさらに多くのエンジニアに会いました。
結論として、実務未経験で優秀な方がたくさんおられました。その経験から、そういった方々を世の中に輩出したいと考え、アイティーエスピーがその挑戦の機会を提供しようと思いました。
Q.採用や人材育成で課題を感じていることはありますか?

IT業界のキャリアパスにも課題を感じています。エンジニアの仕事は新規のシステム開発ばかりではなく、テスト業務、キッティング業務、コールセンター業務、既存システムの運用・保守業務も大きなウエイトを占めています。そのため、例えば開発をやりたいと入社したエンジニアが10年間テスト業務だけをやって、新しい言語の習得やスキルの向上に繋がっていないというケースも少なくありません。私はこの状況も変わっていくべきだと考えています。
弊社の基盤があれば、活躍の場はきっと見つかるはずですから、社員にはそれを存分に活用し、エンジニアとしてのキャリアを積み上げてほしいと考えています。
話を伺いながら垣間見えるのは、松島代表の「挑戦する意欲のある人にチャンスを」という、まっすぐな想いです。ではそのために、どのような体制を整えているのでしょうか?
未経験からチャレンジする場合にフォーカスし、研修制度やフォローアップ体制について伺いました。
Q.研修体制やフォローアップについて教えてください。

実務未経験の方には社外研修として3か月間、プログラミング言語(Java)の基礎、Webアプリケーションの個人開発、チーム開発を学ぶ機会を提供しています。
その際の研修費は全額会社負担しており、またその間の給与も研修期間だからといって減額したりもしません。

研修終了後、目安として最初の3年程度はお客様先のプロジェクト(現場)に参画し、先輩たちの指導を受けながら実務経験を積んでいくとのこと。このような体制を組んでいる理由は、「分からないことをそのままにしないため」と、松島代表は続けます。

技術的な側面はもちろんですが、最も重要なのはコミュニケーションです。分からないことを放置するのは、エンジニアの成長を阻害する大きな要因です。そのため、基本的にはいきなり一人で業務を任せることはせず、複数人のチーム体制を組み、新人をサポートできる環境を整えています。
また、IT業界では常に新しい技術が生まれるため、求められるスキルも日々変化しています。変化の激しい世界でエンジニアたちが成長する機会として、アイティーエスピーでは週1回の勉強会も実施しているそう。

社員が持ち回りでプレゼンを行い、最新の技術や業界トレンドについて活発に議論しています。テーマは担当者が自由に決め、プレゼン資料の作成も自身で行います。
こういった発表の場に苦手意識のある方もいるかもしれませんが、気軽な勉強会なので安心してください。何より大切にしているのは、失敗を恐れずに挑戦する姿勢ですから。みんなも楽しみながら参加しています。
聞けば、松島代表がプレゼンした回もあったとか。

その時の勉強会テーマタイトルは『男性と女性の違い』でした。
目的としては、仕事上でチームを組んだ際の男女間のコミュニケーションについて、社員に理解をしてほしいと考えたためです。
なぜ女性の買い物は長くなりがちなのか、とか、女性から質問された時の模範解答はどんなものかとか。
一方的なプレゼンではなく、参加型にしたこともあってめちゃくちゃ盛り上がりました。
仕事をする上で性別は関係ありませんが、「生物学的な観点で、一般的に人と会話する際、男性はこう考える傾向がある。一方、女性は…」といったように、ゲームを交えて男女の思考回路やコミュニケーションスタイルの違いをプレゼンし、より円滑なチームワークを築くためのヒントを共有したとのこと。

大切なのは、自分の考えをどう分かりやすく相手に伝えるかということです。エンジニアは、単にコードを書くだけではなく、お客さまとの対話を通して、真のニーズを引き出すことが求められます。それはお客さまとの信頼関係を築く上で不可欠な要素です。この勉強会は、そんなコミュニケーション能力の底上げも目的としています。
このような勉強会を定期的に行うことにより、プレゼンテーション能力だけでなく、折衝力や課題解決能力の向上、そして何より、未知のものにチャレンジする精神を育む良い機会になっていると語ってくれました。

社員が伸び伸びと仕事ができる環境づくりに力を入れているアイティーエスピー。労働環境の面でも様々な工夫がされています。
Q.福利厚生など、労働環境について教えてください。

入社したその日から、有給休暇が10日付与されます。休暇の申請もしやすい雰囲気で、子育てしながら働いている社員も居ますが、子どもの急病時等にも柔軟に対応しています。
変わったものだと、社員の誕生日に家族全員分のスターバックスカードをプレゼントしています。また、社員とその家族を対象としたBBQなどの社内イベントを定期的に開催し、社員同士の親睦を深めています。社員も社員の家族も大切にしていきたいので。

行動力と熱意、そして思いやりに溢れた松島代表の原動力はどこにあるのでしょうか。先日、松島代表が中心となり、地元の有志と共に開催した出雲市初の気球イベントは、地域活性化に繋がる企画として大きな注目を集めましたが、松島代表は「個人的な趣味です」と続けます。

社員には積極的に新しいことに挑戦してほしいと常々話していますが、経営者である私も、その言葉通りに行動に移すことが重要だと考えています。常に変化することを恐れず、新しいことに飛び込む姿勢こそが、弊社の成長にも繋がります。常に挑戦し続けることで、自分自身も会社も大きく成長できるものと考えています。
取材に訪れたこの日も、「実はカンボジアから今朝戻ってきたばかり」という松島代表。これも仕事ではなく、純粋な好奇心から生まれた旅だったそうです。
ここまでお話をお伺いするだけでも、松島代表がいかに日ごろから"新たな挑戦"を大事にしているかがひしひしと感じられます。この熱意こそが、アイティーエスピーの社員の皆さんのモチベーションを高く保ち、牽引している理由なのでしょう。
Q.どんな人材を求めていますか?

シンプルに、新しいことに対して好奇心を持てる人ですね。未知の技術や新しいプロジェクトにも積極的に取り組む姿勢が大切ですから。経験は無くても挑戦してみる探究心を持っている人。そういう人なら、これからのアイティーエスピーを一緒に盛り上げてくれると信じています。
Q.最後に求職者の方へメッセージをお願いします。

現在、アイティーエスピー島根出雲オフィスの社員は26名です。社員の8割は実務未経験からの挑戦になりますが、日々成長し、現場で活躍しています。私たちは常に新しい知識や技術を吸収し、成長していきたいという意欲あふれる仲間を求めています。共に未来を切り開いていきましょう!
次にお話を伺ったのは、入社2年目のプログラマー稲川桃佳さんです。 稲川さんは東京から出雲市へIターンしてきたそう。

Q.島根県へIターンしたきっかけを教えてください。

子どもの頃から神話が好きで、特に出雲神話の世界観に魅了されていました。そんな中、神話の舞台が実在する場所だと知り、出雲という土地に強く惹かれるようになったんです。初めは観光で訪れるだけでしたが、神々の物語が息づくこの地で暮らしてみたいという思いが次第に強くなり、最終的にIターンを決意しました。
東京では全く違う業界で働いていたという稲川さん。なぜ島根ではITの仕事を選んだのでしょうか?

東京では介護職に就いており、仕事のやりがいはありましたが、何かを成し遂げたという達成感はあまり感じることができませんでした。また、夜勤や残業でワークライフバランスが取りづらい状況だったこともあり、転職を意識するようになりました。
そんな中、IT業界に転職した友人から、「残業がほとんどなく、子育ての時間を十分に楽しめている。さらに、自分が開発したシステムが社会の役に立っていると実感できる」と聞き、IT業界なら、やりがいのある仕事と私生活の両立が可能なのではないかと考えるようになりました。
Q.島根県での仕事探しはどのように進めましたか?

私の場合、先に出雲市に移住することが決定していたので、仕事も同市内の企業に絞り、ふるさと島根定住財団に相談しながら就職先を探しました。
その中で紹介してもらった企業のひとつがアイティーエスピーだったそう。

特に印象に残っているのは、アイティーエスピーでの最終面接です。島根出雲オフィスの松島代表との面接は、最初はかなり緊張していました。でも、松島代表がフランクで気さくな方だったおかげで、すぐにリラックスして話ができるようになりました。面接が終わった後は、入社前の研修で学ぶことや資格取得の計画を立てるなど、とても前向きな気持ちになったのを覚えています。
「未経験でも本気で取り組む熱意と気概があるなら、それだけで十分」という松島代表の言葉に強く心を動かされ、アイティーエスピーへの入社を決意したそうです。

そして、もう1つエピソードとして心に残っていることがあるのだとか。

ふるさと島根定住財団の方々のサポートにはとても助けられました。アイティーエスピー島根出雲オフィスでの顔合わせの日は、東京から夜行バスで島根に向かい、到着してすぐに顔合わせという、かなりハードなスケジュールでした。でも、財団のスタッフの方が駅まで出迎えてくださり、面接にも同行していただきました。その後、出雲の街も案内してくださり、土地勘のない私にとって本当に心強かったです。財団の皆さんには今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
Q.入社後の研修から現在の業務内容を教えてください。

研修ではプログラミングの基礎を学びました。最初は戸惑うことも多かったのですが、少しずつコードが書けるようになり、画面のデザインが完成した時は本当に嬉しかったですね。小さな達成感を積み重ねるうちに、プログラミングの楽しさに気づきました。
現在はお客様先に常駐し基幹システムの保守を担当しています。主に、Java言語を用いたシステムの改修やバグ修正を行っているのですが、意図したとおりの動作を確認できたときの達成感は格別です。
今はJava SE 11 Silver(Java Silver)の資格取得を目標に、基礎から応用まで幅広く学んでいるという稲川さん。また、島根県が力を入れているRuby言語にも興味を持ち、今後スキル習得に挑戦したいとも語ってくれました。
Q.オフの日はどのように過ごされていますか?

神話にゆかりのある出雲大社や八重垣神社などを巡って休日を満喫しています。島根県は神話の舞台となった名所が多く、ここに住んでいるだけで趣味の探訪心が刺激されます。この地に移り住んだことを、心から幸せに感じています。

移住で夢見た生活を実現させた稲川さん。そのキラキラとした笑顔からは、日々の充足感が伝わってくるようでした。
Q.最後に求職者の方にメッセージをお願いします。

出雲に来た当初は全く知り合いがいませんでしたが、先輩達が親切に仕事を教えてくれたり、趣味を一緒に楽しんだりする中で、すぐに打ち解けることができました。アイティーエスピーにはUIターンで入社した社員が多いので、お互いに支え合える良い環境が生まれています。自分らしく活躍できる場所だと思いますので、私たちと一緒にこの会社で働いてみませんか?
未知の業界にチャレンジしてみたいという熱い想いをお持ちの方、ぜひ一度松島代表の話を聞いてみてください。あなたの人生の新しい一歩になるかもしれません。
(2024年11月取材)